機械や構造物を長期間使用していると、ボルトやナットが知らないうちに緩んでしまうことがあります。
この「勝手に緩む」現象を、工学の分野ではセルフルーズニング現象と呼びます。
一見すると単純なネジの緩みですが、そのメカニズムはとても複雑で、振動や繰り返し荷重、温度変化、摩擦などさまざまな要因が絡み合って発生します。
放置すると機械の性能低下や事故の原因になりかねないため、工場や建設現場、自動車や航空機など幅広い分野で対策が重要とされています。
この記事では、セルフルーズニング現象の基本的な仕組み、発生要因、具体例、そして対策方法についてわかりやすく解説していきます。
セルフルーズニング現象の基本的な仕組み
セルフルーズニング現象は、外部から繰り返し加えられる力や振動によって、ボルト・ナットの締結力が徐々に低下する現象です。
一般的にボルトやナットは摩擦力によって固定されますが、外力が作用すると少しずつ摩擦が破られ、ねじ山同士の相対的なすべりが発生します。
これが積み重なることで、やがて目に見える緩みに至ります。
とくに問題になるのは、緩みが突然ではなく「少しずつ進行する」という点です。
定期的に点検を行わない限り、気づいたときには重大な不具合を引き起こす危険性があります。
 えり
えり実際に、航空機や新幹線などは定期的にボルトをたたき、緩みがないか人がすべてチェックしています。
セルフルーズニングを引き起こす主な要因
セルフルーズニング現象は単一の要因ではなく、いくつかの条件が組み合わさることで発生します。
代表的な要因を見ていきましょう。
振動
機械や車両では振動が常に発生しています。振動によってボルトが微小に回転し、緩みが進行します。
特にエンジン周りや建設機械などでは顕著です。
繰り返し荷重
ボルトが荷重を受け続けると、わずかに伸び縮みしながら応力を繰り返します。
このサイクルによってねじ山の接触面がずれて緩みが生じます。
温度変化
金属は温度によって膨張・収縮します。ボルトと被締結物の材質が異なると、膨張率の違いから応力が変化し、緩みやすくなります。
摩耗と潤滑不足
摩擦が減ると固定力が低下します。例えばグリースやオイルが流れ出してしまうと、摩擦による抵抗が減って緩みが進行しやすくなります。
セルフルーズニングの典型的な例
自動車やバイク
走行中の振動や段差による衝撃で、サスペンションやホイールのボルトが緩むことがあります。特にタイヤ交換後の増し締めが推奨されるのはこのためです。
機械設備
工場の生産ラインでは高速で稼働する装置が多く、ボルトの緩みが製品不良やライン停止につながることがあります。
建設・橋梁
橋や鉄道レールの締結ボルトは、温度変化や通過荷重の繰り返しによって緩むことが知られています。
セルフルーズニングの防止策
緩みを完全に防ぐことは難しいですが、設計やメンテナンスによって大幅にリスクを減らすことができます。
適切な締め付けトルク
ボルトは「強く締めればいい」というわけではありません。設計値に基づいた適正トルクで締めることが重要です。
緩み止め部品の使用
- スプリングワッシャー
- ロックナット(二重ナット方式)
- セルフロックナット(樹脂リング付き)
- 歯付き座金
これらは摩擦を高め、緩みの進行を抑える役割を持ちます。
ねじ接着剤の使用
ロックタイトなどのねじ用接着剤を塗布することで、化学的に固定する方法も広く使われています。
定期的な点検と増し締め
どんなに優れた対策を施しても、使用環境によっては緩みは避けられません。定期点検で早めに異常を発見することが大切です。
まとめ
セルフルーズニング現象とは、ボルトやナットが外力によって少しずつ緩んでしまう現象です。振動や繰り返し荷重、温度変化などが主な原因であり、自動車・機械設備・建築構造物など幅広い分野で問題になります。
防止策としては、適切なトルク管理、緩み止め部品や接着剤の使用、そして定期的な点検が欠かせません。
「ただのボルトの緩み」と軽視せず、セルフルーズニング現象を理解しておくことが、安全性と信頼性の確保につながります。


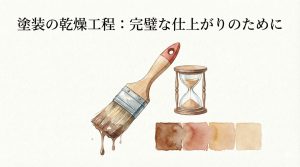

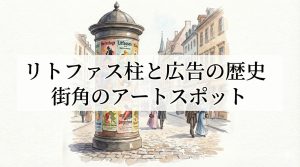
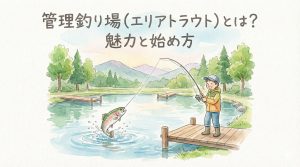
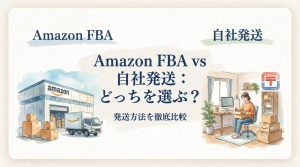
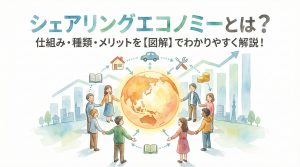

コメント